『梵和大辞典』(講談社)で真言を引いてみましょう。
まず、真言はサンスクリット語マントラ:mantraの訳。
辞書はこの通り。
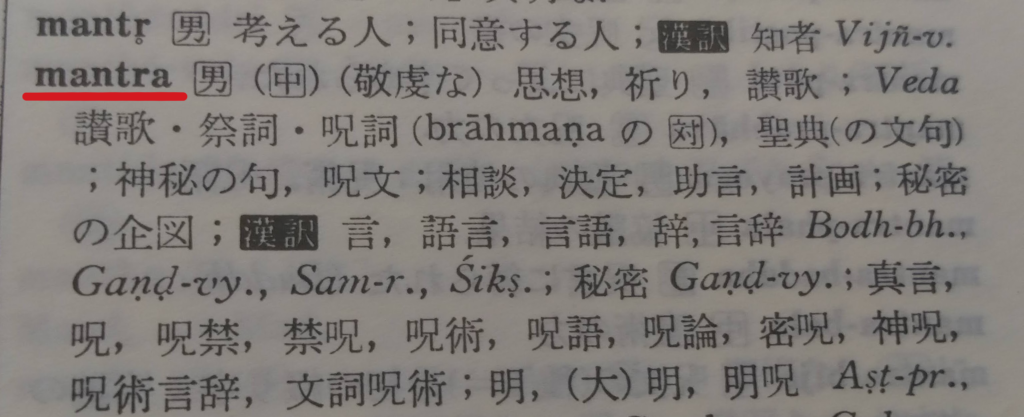
学校では、
「思考する器」と教わりました。
思考して唱える
唱えて思考する、
それが真言。
真言の始まり文句で多いのが、
おん あろりきゃ そわか
などの 「おん」
これは日本語なまりで、言語に近いのは、
オーン、またはオーム、:oṃ
oと eは長母音です。
訳さないことが多いですが、
辞書では、
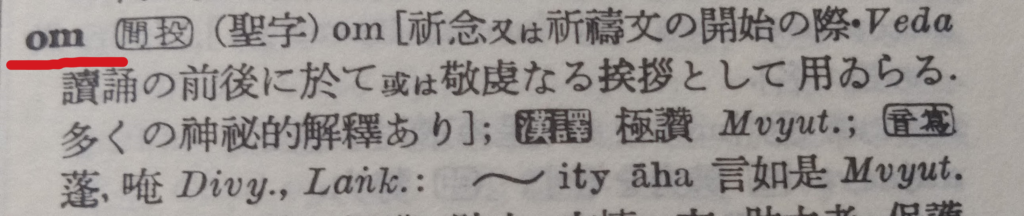
『秘蔵記』27に
oṃ字はa,u,mの三字をもって体となる。
阿字は法身(真理の当体、仏性そのもの、つまり我々であり仏)
塢字は報身(修行して真理を悟った仏)
麼字は化身なり(真理が様々な姿になって現れる仏)
法身はわかりにくい概念ですが、
『日英佛教語辞典』を引くと、
・Hosshin;Dharma-body、the body of the ultimate reality
とあり、少しわかりやすいかな。
真言に多く登場する言葉のひとつが、
紅蓮華のパドマ:padma
日本語なまりで はんどま、はんどぼ
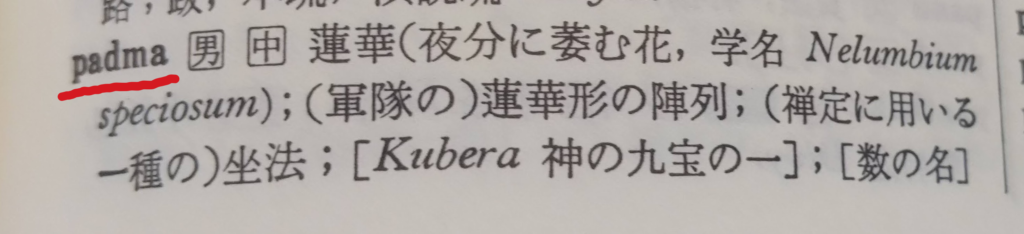

泥中に咲き、泥に染まらない蓮華は清浄心の象徴。
煩悩迷いの中にあって花開き、
それに染まらないのが本来の心。
宝珠のマニ:maṇi もよく真言に登場します。
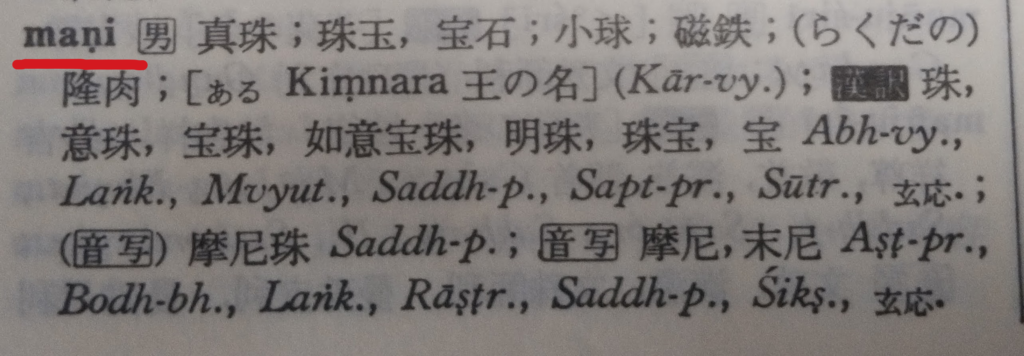

宝珠は、
あるがままの理法、
如来の分身、
あらゆるものの主体となる性質
と『御遺告』第24にあります。
真理の象徴、ということですね。
パドマもマニも、光明真言にあります。
おん あぼきゃ べいろしゃのう まか ぼだら
まに
はんどま
じんばら はらばりたやうん
それから金剛のヴァジュラ:vajraもよく見ます。
日本語なまりで ばざら
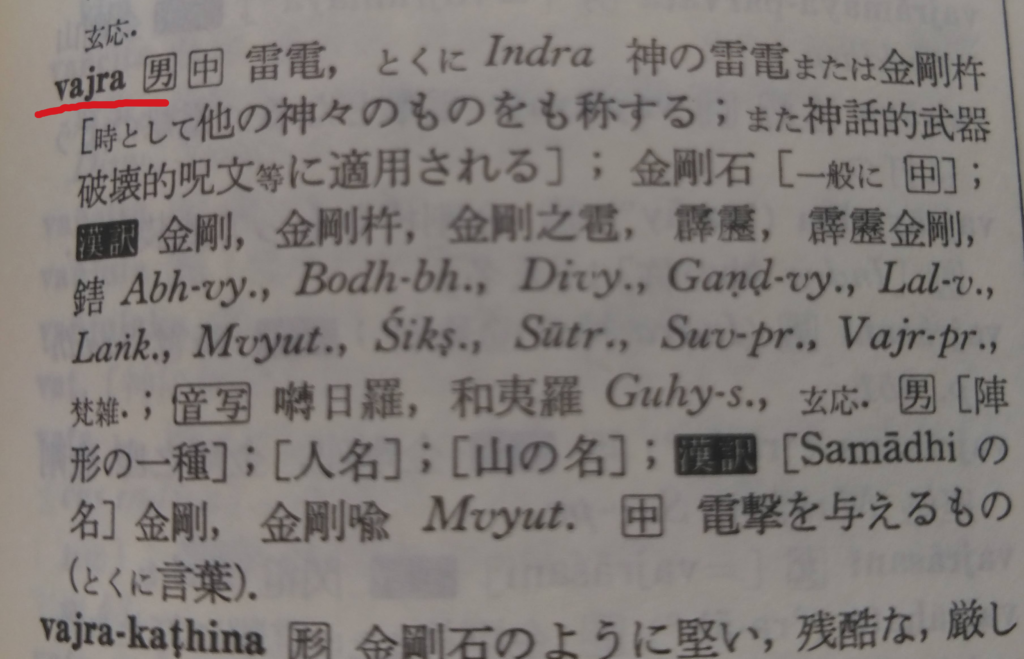

大日如来の、
おん ばざら だーと ゔぁん
お不動さんの、
のうまく さーまんだ ばざら だん・・・
などにあります。
金剛はダイヤモンドのように固いもの、
決して壊れない菩提心(悟りをもとめる、さとりそのもの)の象徴。
また、武器ですから
迷い煩悩魔軍を破るもの。

最後の文句が「そわか」の真言も多い。
これも日本なまりで、
本来の発音はスヴァーハー:svāhā
通常、訳しませんが、辞書には、
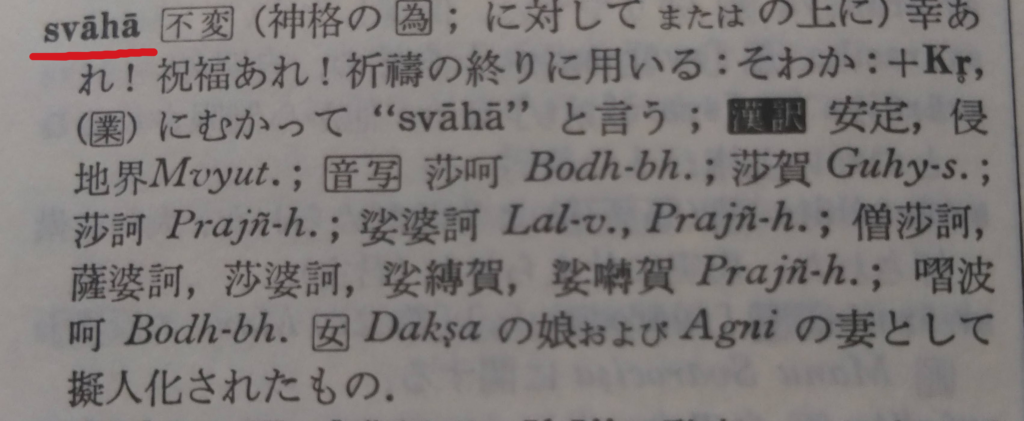
意味を心に染み込ませて、唱えましょう。








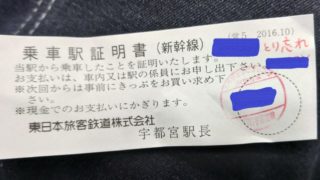






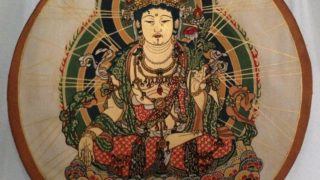










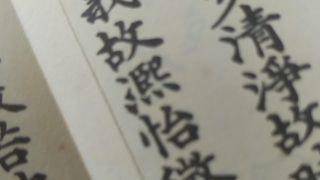


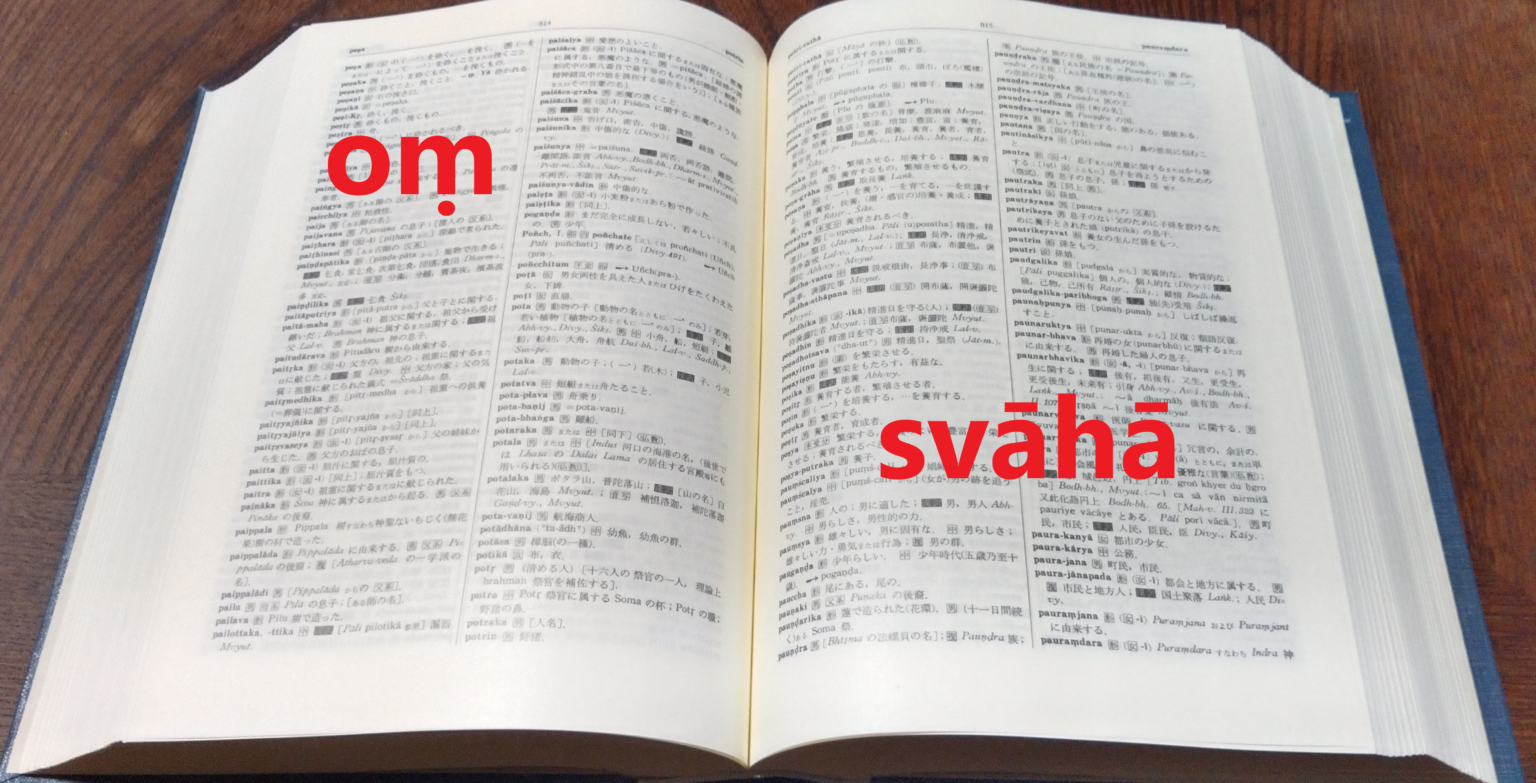


コメント